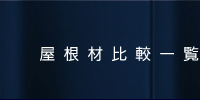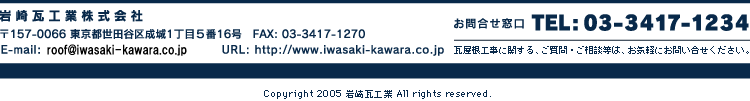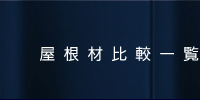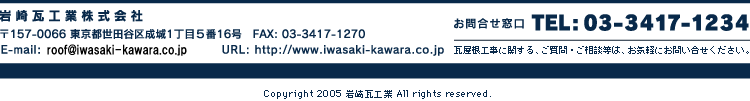|
いぶしの光沢と瓦の厚みによる影が特徴。
ある程度の勾配は必要。古くなる程、味がでます。 |
|
|
|
 |
古来の技術
炭素の膜である
いぶしで撥水。
釉薬はお茶碗と同じ
表面はガラス質。 |
|
|
|
 |
炭素の膜や釉薬質が
熱を反射する。
瓦と野地板の間にある
空気の層が断熱。 |
|
熱伝導率が高いため断熱材が必要。
|
 |
|
融点の高い金属や不燃材を使うことに加えて
火が上に抜けない様、
下地に断熱材や防火材が必要。 |
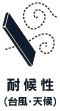 |
一枚毎の釘打ち、新耐風構造瓦で安心。
陽射しや気温変化にとても強い。 |
|
|
| 雪によるすがもれや温度伸縮、風によるばたつきなど自然条件に影響を受けやすい。 |
|
 |
|
10~20年
(10年置きの塗装)
性能の劣化より先に色落ちが始まる。
25年程度で葺替。 |
|
10~20年
| 5年置きの塗装が必要(自然条件、立地条件等により大きく変わる。電触、塩害などにも注意が必要。) |
|
 |
| 「瓦の厚み」と「野地板との空気の層」が外の音を遮断。一般住宅で望ましいとされる30デシベルを完全にクリアしている。 |
|
野地板と密着しているため防音効果は低い。
対策が必要。
|
 |
|
屋根地と接してしまっているため
通気性は望めない。
換気棟の設置を強くお勧めしております。
|
 |
|
| 基本的には葺き替えか塗装。 部分的な補修には向いていない。 |
|
| 大抵の場合は部分的な修理が可能だが金属疲労による劣化が伴う。 |
|
 |
65(kg/㎡)
現在の施工法なら安心。(重みは従来の3分の1に)
耐震施工で確実。
|
|
|
 |
初期費用は他と比較すると高いが維持費が掛からない。
(費用は約20年で他より安くなります。) |
|
| 初期費用は安いが葺き替えのサイクルは早くなる。 見た目ではわかりにくい屋根の下地の痛みで余計に料金がかかってしまうことがあるため早めの点検がお得。 |
|
丈夫なほど高くなり、維持費も掛からない。
鉄からチタンまで価格は素材しだい。 |
|
 |
いぶしは大気の埃や空気の汚れを吸い付ける効果がある。
同じ形のまま再利用。 |
|
| 2004年頃以前のものはアスベストが入っている。処分費高い。 |
|
リサイクル可能。 |